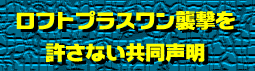 |
|---|
「ブント」機関誌『SENKI』928号(98年1月15日発行)に掲載された
「ブント」の主催する集会「12・14グラン・ワークショップ」での
山崎カヲル氏の講演記録
特に最後の節「対話の例外をつくってはならない」
に注目
12・14グランワークショップでの講演から
制限された対話から全般化された対話へ
山崎カヲル
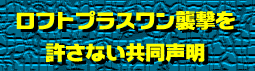 |
|---|
「ブント」機関誌『SENKI』928号(98年1月15日発行)に掲載された
「ブント」の主催する集会「12・14グラン・ワークショップ」での
山崎カヲル氏の講演記録
特に最後の節「対話の例外をつくってはならない」
に注目
「コウモリの話」という表題に、とまどう方もいらっしゃるかと思います。わたしのつとめ先の近くにコウモリがすくっているんですが、夕方になりますと三十から四十のコウモリが乱舞するという楽しいシーンが見られます。でも、そのコウモリの話ではありません。
『イソップ物語』に出てくるコウモリの話というのを、どこかでお聞きになったことがあるんじゃないかと思います。イソップは紀元前六世紀頃に、ギリシャに生きていたといわれる人ですが、彼の有名な寓話集の中の話です。トリとケモノが戦争をしたときに、トリの方が優勢になるとコウモリは「オレは空を飛ぶんだから」とトリの仲間になろうとし、ケモノの方が優勢になると「オレは卵を生まない」とケモノの側につこうとした。そういうことを繰り返した結果、結局トリとケモノが和解した段階でどちらからもつまはじきになって、こうもりは仲間に入れてもらえませんでした、というお話であります。この話は、実はギリシャにおいて内戦がどう考えられていたのかということと、非常に深く関わるんですが、その辺のことはおいておきます。今日はそのコウモリを擁護するという話であります。
対話と理性から排除される人々
そのためにちょっと大上段に構えて、市民社会の問題というところから入っていきたいと思います。思想史的に申しますと、ヘーゲルの段階で、それまで渾然一体として議論されていた国家と市民社会が分離され、解読されるようになってきました。われわれはマルクスを通じて、そういう市民社会と国家の分離を大前提とした上で国家論を論じる、あるいは社会を論ずるというのが基本になってきているわけですね。
その場合、市民社会というのは階級関係が織りなす場とされています。通常の理解によると、その上に国家が調停的にそびえたつ。市民社会というある種の共同性に対して、さらにそれを包括するより高次の共同体が国家であるという理解です。市民社会が国家を規定するというようなことも言われますが、実はかならずしも正しい考え方ではありません。 それというのも、市民社会を構成する「市民とは誰か」を決定するのは国家の役割でありまして、市民社会の輪郭を構成すること自体が実は政治的な行為です。その結果、市民社会から排除されてしまう人々が常に生まれてしまうという意味で、市民社会は非常に根源的な暴力性を伴っているんですね。
そうした排除されてしまう人々の問題というのを、今日はちょっと話をしたいと思います。あまり長い時間がありませんので、非常にはしょった話になるかもしれませんが、その点は容赦してください。
マルクスのように市民社会を階級関係が織りなす場として見るなら、階級対立の場、階級闘争の場ということになってしまいます。ところで戦争については、クラウゼヴィッツという人がドイツ語でそれをSpiel(シュピール)、つまりゲームと呼んだことがあります。実際市民社会におけるどんな関係も、一連のルールに従わなければならない。そういう意味でゲームということができます。階級闘争もゲームにほかなりません。しかしながら市民社会ゲームは参加する人間の資格が限られています。たとえば政治に関与する権利というのは日本では二十歳以上の成人にしか与えられていない。つまり未成年はそこに参与する権利がない。それから、日本国籍を取得していない「在日」の人々も政治のゲームに参加する資格がない。もちろん短期滞在の人々やいわゆる「不法在留」の労働者たちも同じです。ご存知のように、第二次大戦に破れるまで女性も政治に参加する資格はなかったわけです。
要するに誰がゲームに参加できるかという、ある種の前提的なルールがあります。逆にその前提的なルールによってあらかじめ排除される人々が市民社会概念には、必ずつきまとうんだということですね。したがって、その人たちの問題は、いわゆる国家権力の問題として処理できない。つまり国家権力の奪取というような形では解決できない問題としてあるということになります。それではどういう人々が市民社会に入場できないのかというと、古代のギリシャぐらいにまでさかのぼらなければならないような深い根っこがあるんですが、その辺はちょっとおいておきます。
いずれにしても、市民社会は対話的な理性を持っている人々についてなら受け入れるとされています。あるルールにしたがって対話をおこない、その対話の結果を尊重し受け入れると見なされた人々だけが、対話的理性の持ち主だとされるんですね。しかし対話的でないとみなされた人間たち、あるいは対話の必要がない、声を出すべきではないという人たちというのは、そこから排除されてしまう。最近ハーバーマスの言う対話的理性ということがよく取り上げられていますが、逆に声を出さない、沈黙のうちにおかれる人々が、対話と理性の双方に関わらないといって排除される可能性というものも、常にあるわけです。
「市民社会」概念の再検討
ここですこし、太田昌国さんもふれた、ペルーのトゥパク・アマル革命運動のことを考えましょう。あるいは、ぼくが全面的に共感をしているメキシコのサパティスタ民族解放軍についてもふれたいと思います。彼らがもっとも強く要求していることは何かというと、「市民社会との対話の空間を開け」ということです。自分たちは市民社会の外部にいて、内部の人々の対話の中に入っていない。われわれを外に押し出して沈黙のうちにおかせている市民社会と対話する空間をつくってくれというのが彼らの行動なんです。その空間を開くための手段として、大変ドラスティックな方法ですが、サパティスタは一九九四年の一月一日に武装蜂起をし、トゥパク・アマル革命運動は日本大使公邸の武力占拠をした。けれども彼らの目的は、武力を行使することで、それまで拒まれてきた自分たちの対話の可能性を社会的に認めさせるということに非常に重要なポイントをおいていたんです。ですから、彼らの行動は軍事行動であったと同時に非常に高度に政治的・社会的な行動でありました。
このような形で市民社会との対話を要求する人たちがいたということは、市民社会の側が彼らへの対話の可能性をこれまで拒んできたという事実を明らかにしてくれるわけです。したがって、われわれが現在の社会のことを考え、将来つくるべきよりより社会を考えるとき、市民社会と国家の組み合わせだけで考えることはできないんです。
そういう人々が存在して、この二〜三十年の間、次第にいろいろな形で声をあげはじめました。たとえば私はゲイやレズビアンなどの同性愛者たちとつきあっています。彼らは日本の中ではずっと陰微な差別の対象でありました。ご存じの方もいるかと思いますが、その彼らのなかで「動くゲイとレズビアンの会」が、東京都を相手に「青少年の家」の使用をめぐって裁判闘争をやり、一審二審で勝利した。そういう形で声をあげはじめている。世界のいたるところに存在する先住民たちも、自分たちの声をあげはじめている。在日外国人たちもそうですね。そういう人々も声を上げはじめている。少しずつわれわれの社会は、これまで対話のルールの外においてきた人たちとの対話や交通・交渉を行なわなければならない時代に入っているということです。
彼らはこの社会における平等な権利はもちろん主張しますが、それだけでは決してありません。いま申しましたような市民社会の概念の根底的な変更も要求しています。自分たちを含めるような社会概念を新しく定義しなおせということを掲げているわけです。その意味では一九世紀的な市民社会概念というのを私たちが引きずったままで二一世紀に突入することは、もう不可能であるといってもいいのではないか。彼らの声を聞き、社会概念を彼らのところまで拡張すること、そのための対話をそなえていくことが非常に重要になっていると思います。そして、これまではたらいてきた非常に陰微な排除の論理やそれに象徴される暴力をなくす必要がある。そのことで対話の可能性を極限まで大きくしていくことが今後のわれわれにとって要求されている非常に大きな課題ではないでしょうか。
「ハイブリッドな世界」の可能性
実はコウモリの話はそこにかかってくるんです。これまで市民社会が交通を拒否した人たちと全面的な交通関係に入らなければいけない。そうなると、今までのようにAとBはまったくことなるということでは通用しなくなる。市民社会の内部と外部というのはまったくことなっているのではなくて、両者のあいだに重なった地域、グレーゾーンが出てきます。このグレーゾーンというのは、「どちらでもないし、どちらでもある」ような地帯になります。どちらでもあるということは同時に、形式論理的にいうとどちらでもないという資格を付与されるわけです。要するにどっちつかずのコウモリのような存在になるんです。
いま、ポスト・コロニアルという議論がそうした世界やそうした人々のことを積極的にすくいあげ、ハイブリッドすなわち雑種と名付けています。このハイブリッドな世界がいたるところで広がっている。ぼく自身が大きな関心を持っているテキサスとメキシコの国境地帯では、テクスメックスという非常に特別な言語が浸透しつつあります。テキサス系スペイン語とでもいうか、非常になまりの強い言語で、正規の英語を学んでも英語の部分はわからないし、正規のスペイン語を学んでもスペイン語の部分がわからないというガチャガチャな言語です。そういう言葉がどんどん浸透し、テクスメックス的な言語をバックにすばらしい詩を書く人たちがでてきた。パフォーマンス・アーティストや画家など、いろいろなものがそこからでてきています。
こういうハイブリッドな世界というものが今後開けていく可能性がある。そのハイブリッドな世界が、いま非常にダイナミックな展開をしている。そのハイブリッドな世界を開くためには、旧来の市民社会という概念をわれわれが突き崩して、市民社会内部でのゲームの規則、対話の論理というものをそういう人々を包含できるような形に変えていかなければなりません。その結果としてはじめてその人々との交渉が開始されるわけです。
このように社会概念が変容するならば、ヘーゲル的な意味での市民社会概念の上に構築されていた旧来の国家観というものも、形が変わらざるをえないと思います。その国家論と結びついてきた革命論も変容を余儀なくされる可能性もある。いずれにしても、二一世紀のとば口くらいのところにいるわれわれが大胆に進んでいくためには、そういうハイブリッドな存在を可能にするような交渉が必要だ。それをどのように社会の内部と外部に関係しながら作りだしていくか、ということが大切になるのだろうと思います。
そういう意味で、これまでのような一定の人々に制限された対話ではなく、例外を設けない全般化された対話というものがわれわれには要求されているんだということです。よく、レヴィ=ストロースの言葉をつかって 「制限された○○から、一般的○○へ」という言い方をしますが、まさに「制限された対話から全般化された、一般化された対話へ」とわれわれがどうやって前進できるのだろうか。そこに実は国家の問題や革命の問題、さらに現在、いろいろな形で進展しているハイブリッドな文化やハイブリッドな文化を背景にして花開きつつあるいろんな社会運動がかかわってきます。そういうものがはじめてわれわれの視野に入ってきた。われわれの視野に入ることによってわれわれ自身の社会選択の幅がより大きく、より豊かなものになってくるだろうと思います。