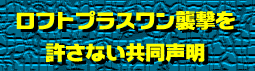 |
|---|
鈴木邦男「夕刻のコペルニクス」論評を |
|---|
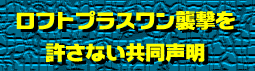 |
|---|
鈴木邦男「夕刻のコペルニクス」論評を |
|---|
この「SPA!」に連載している鈴木邦男の文章で事件を知ったという人は少なくない。しかしその内容は、ぼくにとって違和感を覚えるところが多かった。
そもそも事件の発端をつくった7月8日の荒−鈴木対談の描写からして、あまりに主観的すぎて、読者の脳裏に事実に反する像を結びかねない。鈴木によれば、この日の様相は「観客席にいた『青狼会』佐藤悟志君らの罠にはまり(荒が)『人民裁判』にかけられた。ロフトは怒号と罵声の糾弾集会になった」というものだったという。
しかし本当にそうか。ぼく自身は7月8日の現場にいなかったが、当日その場に居た人に聞くとかなり違う。
「レジにいたら、次々と7〜8人の団体さんばかり来るんです。珍しいなあ、何かのサークルだろうかと思ったら、トークが始まってすぐブントの人たちだと分かりました。みんなで左翼調のヤジを飛ばすからね。60〜70人といったところだと思う。」(加藤梅造/ロフト店員)
「普段は7時過ぎに行けば座れるんだけど、この日はすでに満員だった。一般の客は20人いないんじゃないかな。残りは全部戦旗。」(神坐高徳/一水会事務局)
「戦旗だけで満杯だった。なぜ分かるかっていうと、明らかに団体さんという雰囲気だし、荒の発言にそろってワーッと反応するから」(玄田 生)
「すごい人の入りだった。あれだけ人がいっぱいになるのは珍しい。なんでこの企画で人がこんなに来るんだろうって驚きました。店内に入れなくて、スタッフルームでモニターを見てた。そこにも15人くらい座ってましたね」(エルキン/常連客)
この状況の中で、荒に批判的な発言をしていたのは何人か。
「佐藤さんの他数人。佐藤さんはまあいつものやり方でしたね」(エルキン)
「発言をしていたのは5人くらい」(神坐)
「5、6人かな」(玄田)
主観的な話になるが、人民裁判という印象を持ったかも訊いてみた。
「人数の違いが圧倒的なんですよ。人民裁判とはとても言えない」(神坐)
「いや、あの程度のことで人民裁判という言葉を使うのはどうかと思う。荒も言い返してたし、前列のブントの防衛隊の連中が立ち上がってヤジってたし、人民裁判というよりは互角の言い合いじゃないかな」(エルキン)
「あの人数に批判されるだけで人民裁判になるんじゃ荒って何ですか。ぼくは皮肉ぐらいは言ったけど礼儀は守ったつもりだし、ミゲルは酔っ払って茶化していただけだし、吠えてたのは佐藤だけじゃないの。荒に質問すると前にいる戦旗の連中がヤジりまくって恫喝をかけるんです。佐藤が発言すると、ヒラヌマ!、ヒラヌマ!(佐藤の戦旗時代のゲバ名)、お前がそんなこと言う資格があるのか!って一斉にヤジる。それでたまにロフトに来る右翼の爺さんに『うるさい!人の話をちゃんと聞かんか!』って一喝されてました」(玄田)
会場は60〜70人ほどの動員されてきたブントメンバーで埋め尽くされていた。それ以外の一般客は十数人ほどで、その中で荒に批判的な発言を行ったのはせいぜい5〜6人。発言者の中で「大声で怒鳴り、からんだ」と言えるのは佐藤ぐらいのものだった。「会場を怒号と罵声で騒然」とさせたのは、むしろ佐藤らの発言を封じ込めようとブントメンバーが一斉に行ったヤジであった。
先に取り上げた証言者のうち、7月8日に発言したのは玄田のみ。エルキンと梅造は『共同声明』の賛同者でもない。実は、ぼくが当日の様子を訊いたのはこの4人からだけではない。他の人に訊いても、状況や、人数など、多少のバラつきはあるものの、ほぼ共通している。 ぼくは人数のことだけ取っても、糾弾集会、人民裁判とはとても言えないと感じている。そもそもこの時、数人の批判に晒されていたのは、愚直に生きてきた靴屋の老主人でもなければ、窓際に追いやられた電器メーカーの係長でもない。人間解放の前衛を自認する政治組織の指導者なのだ。
ぼくの感じた違和感は、「糾弾集会」の描写にとどまらない。例えばイベント終了後に「荒さんたち」が「佐藤にけしかけられた。鈴木にだまされた」と怒ったとあるが、ちょっと信じ難い。少しでも鈴木の日頃の言動を知っていれば、彼がそんなことをするとは思わないだろう。だいたい荒は、鈴木が、浅野健一と共著を出すような「リベラルな右翼」であることを知っていたからこそ対談を行ったはずだ。また佐藤とブントの縁は鈴木よりも古い。鈴木を知り、佐藤を知るブントメンバーが「鈴木にハメられた」などと本当に思うだろうか。もちろん勢いでそんなことを口走った人もいるかもしれないが。
結局ここに表明されているのは鈴木の主観なのだと受けとめるべきなのだろう。鈴木は、以前から顔を知っている佐藤が、自分のゲストを不愉快にさせることで鈴木の「顔を潰した」と感じている。
しかしそれにしても彼が事件の本質を全く理解していないのはどういうわけだろうか。鈴木は「戦旗派の気持ちが痛いほどわかる」という。「暴力に訴えた方が悪い」のは確かだが、「左右を越えた」「建設的話し合い」をぶち壊した佐藤への怒りの方が大きいというのである。だが「暴力に訴えた方が悪い」などという捉え方では、ただのケンカと今回のような組織的暴力の区別は付かなくなってしまう。
鈴木が事件をこのようにしか捉えられない背景には、彼が常日頃語っているテロリズム論の限界がある。
鈴木によれば「左右を問わず」社会変革を志向する人々がテロに走るのは、少数派たる自分たちの主張を訴える場がない焦りがあるからだという。だから社会が少数派にも発言の場を与えることが、彼らが「思いつめて」テロに走るのを防ぐ道である。鈴木が「左右対話」を推進するのも、この延長線上にあるのだろう。考えの異なる者同士が対話してゆくことで、暴力なしで世の中を良くすることが出来る…。
しかしこれで現実の様々なテロリズムを説明することが出来るだろうか。
そもそも彼が長く身を置いてきた右翼によって行われているテロルについてさえ、この規定は全く役に立たない。例えば全国の封切館で東條英機を讃える「プライド」が上映されている時、勇気ある経営者によって単館上映される「南京1937」が、数十台の街宣車によって包囲されるとしたら、これを少数派の焦りと言えるだろうか。なけなしの金を集めて市民団体が開いた「731部隊展」の会場で消火器をぶちまけるのが少数派の焦りなのか。そもそも大マスコミをも震え上がらせる、日本でその名に価する唯一のタブーである天皇制を、印籠の如く振りかざす右翼がホントに「か弱い少数派」と言えるのだろうか。
言論の萎縮・封殺を目的とするテロの現実を具体的に検証していけば、レーニン主義とか天皇主義とかいった、テロルの行使者が掲げている思想の内実に批判的切開の目を向けることは避けられない。天皇制についてふれずに右翼テロについて考えるなどという芸当が出来るわけがないのだ。しかし、テロの否定のために、その思想的起源を問う道を進んでゆくことは、鈴木が右翼で居られなくなる危険性をはらんでいる。
鈴木は、そうした検証に踏み込むことをせず「暴力はいけないなー」「話し合わなくっちゃー」といった一般的な「べきだ」論の水準でテロに「反対する」道を選んだ(「絶対平和主義者」として「ガマン」してきた!)。それによって鈴木は「リベラルな右翼」となりえたのである。
誰が、いかなる思想に基づいて、どのような質のテロルを行使しているのかということを直視することを避けながら一般的に暴力に反対しようとする時、無意識の自己欺瞞が生じる。鈴木の文章の中で街宣中の右翼が左翼に殴られて云々という「たとえ話」が出てくる。だが、情宣中の左翼を殴りに来る右翼はいくらでもいるが、その逆が果たしてあるのだろうか。「人が犬を咬めばニュースになる」と言われるが、この「たとえ話」のようなニュースはついぞ聞いたことがない。
こうして、鈴木の暴力への一般的反対は、現実に行使された暴力の質を分別出来ないという事態に陥る。「中傷ビラ」を一人でまく男の「無礼」と、数十人の取り巻きに囲まれた前衛党の親分に食ってかかる数人の「秩序かく乱」と、待ち伏せて行われる「組織的テロル」が、鈴木にとってはひとしなみに同じ「暴力」になってしまう。それどころか、「戦旗派の気持ちが痛いほど分かる」のである。なにしろテロの反対語である「建設的話し合い」をぶち壊したのだから、佐藤こそがテロリストなのである。
しかし……。
ぼく自身も含めて、多くのノンセクトの友人たちが新左翼党派のリンチや恫喝を経験しているし、右翼に襲われたことも何度もある。その中には他ならぬ一水会も含まれている。右翼が警察と連携して動いているとしか思えない状況も体験した。そうした現実と無関係に和やかに終始する「左右対話」なるものに、ぼくは何の生産性も期待できない。「左右」の親分の平和なんてウンザリだ。
ぼくは、鈴木のネアカぶりがもたらした解放感というものは否定しない。開かれた対話の可能性を追求することにも異議はない。しかし「違いを認めあう」といった趣旨のもとで「左右仲良し対談」を繰り返しても、「世の中を良くする」ための何一つ産み出せないのではないか。「左右を越えた反体制」などといったかけ声は、右も左も分からない反体制気分で宴会を盛り上げるのが関の山だ。金日成主義者と天皇主義者が、安心して、「反米」を語り合うような宴会は、断じて「建設的」ではない。
肝心なことも避けずに話し合う討論、相手を変え得るし、自分も変わり得る討論には緊張が伴う。終始和やかというわけにもいかないだろう。しかしそうした対話においてはじめて「事実と道徳的な良心に基づいた誠実な討論」(荒岱介)が成立する条件を、本当に追究する必要が出てくるのである。そうした追求の中には、当然思想そのものの検証も含まれる、その思想が果たして対話の緊張に耐え得るかどうか。思想を越えた対話と言っても、対話を破壊し凍らせる思想というものが、世の中には実際にあるのだから。